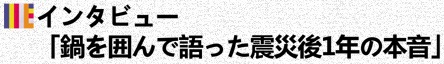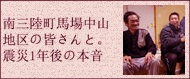南三陸町馬場中山地区の皆さんと。鍋を囲んで語った震災後一年の本音。

|
|
 左上:阿部倉善さん、左下:三浦千代子さんと阿部初恵さん、右上:阿部きくみさん。 |
――震災が起こって、津波が押し寄せてきたときのことを話してもらえますか?
阿部倉善さん 一番つらかったのは、自分の家が流されていくのをこの目で見たときだな。1回目の津波でワカメ工場が流され、これは危ないと高台の集会所(馬場中山生活センター)まで逃げて、後ろを振り返ると、2回目の大津波がわが家に押し寄せてきて、一瞬のうちに流されてしまった。あのときはもう終わりだと思った。家もなければ船もない。全財産が流されてしまったんだからな。1回目の津波の後、船だけは助けたいとは思ったけども、3カ月になる孫が家にいたんだ。船が大事か、孫が大事かの選択をしなければならなかった。それで、船はあきらめて、家族とともに高台に逃げたんだ。正直、目の前が真っ暗になった。
最知隆さん 「もし~たら」の話ではないけれど、地震の後、すぐに船を出しておれば、間にあったかもしれねえなァ。100メートルほど沖へ行ったら船は助かった。しかし船を出さなかったあの判断は、いまでも正しかったと思ってる。これまでも大津波警報が出たことがあるけど、津波は来なかったり、来てもちょこっとだったり…。
今度のは絶対に来ると分かっていて命がけだったからね。船を出していたら家族に犠牲者がでていたかもしんねえ。
倉善さん こういうことは語りたくねえんだ。1500万円かけて買った船を捨てて、俺は家族を取ったんだ。
 左上:皆で美味しい鍋をいただいた。左下:阿部浩さん。右下:三浦善浩さん。 |
三浦善浩さん はじめは俺も家は大丈夫だと思ったから、船を出さねばと思った。 その時「船諦めて、家を守れ」と言われて、船さ、あきらめて、家に帰って家族を守ったの。家は流されたけれども、人は守れた。隣の夫婦は、庭先で第一波を見て、大丈夫だと思ったのか家の中に入って、第二波で家ごと流されてしまったんだ。
倉善さん 船出して、家族なくしたら、どうなるんだ。俺、船いらねえよ。家族だよ。
善浩さん 俺だって家族がいなくなったら、ここにおられねえ!
――初恵さんは、ご主人のお母さんが津波で流されたんですね。
阿部初恵さん 義母は志津川病院に入院していて、点滴の管が外せず、歩けない状態でした。それでも、一度家に帰ることになっていたんです。
その日、病院で介護相談を受け、買った入れ歯を病室に置いて帰ったのですが、帰り際、お義母さんから「寄り道しないで、早く帰りなさいよ」と言われたんです。それが最後の言葉でした。お義母さんのおかげで、私は寄り道せずに自宅へ戻り、夫(浩さん)と娘と3人で行動して、津波に襲われずに済んだんです。私ひとりだったらどうなっていたか分かりません。しかし義母は病院の4階にいたにもかかわらず流されてしまって、唯一、私が置いてきた入れ歯が見つかり、7月末、それをお墓に納骨し、葬儀をしました。
でもいまだに亡くなったとは信じられず、どこかにいるような気がします。お義母さんは、果たして成仏してくれているのか、心配でした。先日、お坊様から「成仏していますよ」と言われ、わだかまりの心が融けるようにフーッと抜けて、楽にはなりましたが…。
阿部きくみさん 私とこは、お父さん(夫の倉善さん)の親父さんが震災の1カ月前に亡くなったのだけども、震災でお義母さんが亡くなって、私のおふくろも亡くなって、義姉ら7人の親族が亡くなってしまったんだ。
――皆さんは、いのちが助かって、この馬場中山生活センターで避難生活が始まったのですね。
倉善さん 最初は水も食料もねえ状態で一夜を明かした。次の日、海岸さ行って、米拾ってきてみんなで泥と石をコツコツ洗い流して食べたんだ。だども、200人いたから全然足りないの。それでかぼちゃとか入れて喰ったなあ。
きくみさん お米を炊こうにも炊く釜がないからこのお鍋で煮たんだけども、八升から一斗ほど煮なければならないんで満杯状態。それを4回も繰り返すんだよ。
強火で煮るから、周囲はビリビリ焦げて中は生状態で固いまま。これではダメだというんで、お粥にしたんだ。菜っ葉や白菜、かぼちゃなんかを入れて。
――ずいぶんと不自由な生活だったのですね。
三浦千代子さん 不自由とか不安とか感じる余裕はなかったですよ。その日その時を懸命に生きて、考える暇はなかったですね。次から次へとやることがあって、3度の食事の支度とか、後片付け、トイレの掃除とか…。それで、分担を決めて、みんなで協力してやったから、不平やもめごとはなかったですね。
きくみさん 1日が終わって寝る前はワイワイガヤガヤと飲むのが楽しみにもなった。 いろんな出来事があって失敗もあって、明日はこうしようよ、とか言って反省会して、それが楽しかったべな。
隆さん 俺は隣村の名足保育所に避難してた。
道路が通れねえから馬場中山生活センターには来れなかった。3日間食べ物もないし、動けなかったからね。
倉善さん 海岸沿いの道路しかなくて、それが潰れたから孤立した。だから、未来道プロジェクトを完成させねばならなかったんだ。
隆さん これからは孤立することはねえな。志津川のベイサイドアリーナなど大きな避難所には、すぐに救援が入ったけども、我々みたいな小さな所はどこも孤立していたとも言えるけど。
倉善さん 食料でも何でも、本部(役場)から援助もらったのは1カ月後だからね。本部のアリーナに行くと、俺たちの避難所には170人も暮らしていたのに、ねぎ3本、ごぼう6本、玉ねぎ5キロだけだったから。頭さ来たから、そんなのいらねえって帰ってきた。
――生きるのが大変な状態から、今は復興に向けて未来道を作り「なじょにかなるさープロジェクト」という漁業復興計画を立ちあげられた。沈みがちな心を奮い立たせ、もう一度希望を持って生きていこうとされたキッカケは何でしたか?
倉善さん それは、全国から毎日のように救援物資やら、直接応援に駆けつけてくださるボランティアの人たちがおられたからだべさあ。千葉馨さんにインターネットで支援を呼び掛けてもらったりしたお陰もあって、野菜やら飲料水やら、果物や魚、いろんなものが届けられるようになったし、毎日、様々な人たちが来てくれて、俺たちの身を案じてくれたんだ。
千代子さん 私は、被災してすべてを失い、途方に暮れていたときに、登米市の蛯名さんから「苗プロジェクト」の話があり、野菜やたい肥を届けてもらいました。避難所で苗を受け取るおばあさんたちの嬉しそうな顔を見て私もうれしさがこみ上げて来て…。おかげで素晴らしい野菜ができ、人と人の交流も進みましたよ。
隆さん 俺はボランティアの人たちに家の周りを片付けてもらった時に、「何が一番助かりましたか?」と聞かれ「あんたたちがここにいてくれることが一番助かった」と答えたんだ。だって、自分では何から手を付けて良いかわからなかったもんね。ボランティアの人たちが俺たちに立ちあがるキッカケを作ってくれた。
倉善さん 俺たちは船も仕事場も家もなくなった。だども、船がなくなっても、カモメはカモメだ。俺たちゃ、海で生きるのが一番合っているということだべ。それで「なじょにかなるさー」のプロジェクトを立ち上げたんだな。
善浩さん ワカメの養殖が当面の目指すところだ。俺自身、20代でワカメ養殖を始めて20年かかってやっとここまで来たかと思ったところで、震災だもんね。はじめは船も加工機械もなくて、こつこつと重労働でやってきた。それで船を持ち、機械化も済んでこれで楽に仕事ができる、豊かな生活ができると思った矢先に、何もかも津波に持っていかれたんだよね。完全に打ちのめされたんだ。もういいやと、やる気をなくした。それをやる気にさせてくれたのは、ボランティアの人たちとか、ここを訪れてくれるいろんな人たちだよ。来ては「頑張れよ」と励ましてくれる。そのうち、このままじゃいけないと思った。結局、俺たちは漁師で喰ってきたわけだから、やっぱり漁師に帰らなくちゃならない。もう1回やるしかないと思ったわけよ。
――ところで、ワカメ養殖をするには船が欠かせないそうですね。その船を買いに、北海道まで行ったのですね。
隆さん とにかく、どんな船でもいいから、1艘持って帰らねばと思った。ブローカーが入ってきて、交渉は難しかったけども、たまたまワカメ養殖船に適した5トンの船が見つかって買ったんだ。
ところが、船主から明日は天気が荒れると言われ、大急ぎで夕方4時半に出港した。俺たち4人、みんな操縦は初心者。だども、津軽海峡という難所をレーダーもない船で渡らねばならねえ。命がけというか命知らずのかじ取りだったよな。なにしろ危険だとか怖いとかの意識はなく、ひたすら馬場中山に帰らねばという思いだった。それで4日目の早朝に帰れたんだ。
――復興に向けて着実に前進しているところですね。
倉善さん 今はお金もなくて、今年収穫できるワカメでは生活ができねえ。でもやるしかねえんだ。来年は倍に増やし、次の年は、と一歩一歩進むしかねえんだ。
善浩さん ワカメ養殖は、種を植え付けて水揚げするまで何もすることがないし、いったん水揚げしたら次の年まで収入がない。その間、もどかしいし、つらいよ。今年は震災前の3分の1くらいの収穫しかないんだ。赤字覚悟なんだ。
隆さん その収穫したワカメを加工する場が必要になる。それと、それをどう販売していくかだな。先のことを考えると眠れないよ。でも、これだけ震災にやられたけれども、つながり、絆も生まれたということだ。俺たちはポジティブに考えて行くことにしている。
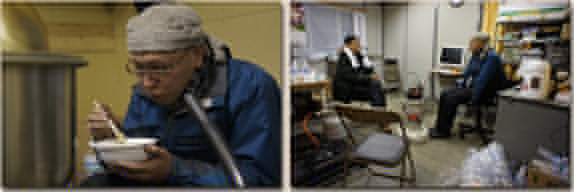 千葉馨さん |
――最後に、この場を設定してくださった馨さん、ひとこと。
千葉馨さん 自分は、インターネットで情報発信することのすごさをこの震災で知りました。人と人がつながりを持つこと、それがいかに大事であり、そういう役割を自分が担えることに喜びを感じているところです。――Fin.
![]()
 |
注1 本インタビューは2012年1月に行いました。その後、皆さんが作られたワカメは「福福わかめ」と名付けられ、千葉馨さんが運営されているネットショップ:馬場中山カオル商店で4月から販売されました。(左の写真) 注1-2 ワカメレンジャー参上! 同地区の女性たちの生活再建の一助とすべく、愛らしいキャラクター「ワカメレンジャー」も誕生しました。ぬいぐるみのキーホルダーで、1個につき400円が作り手に渡されるというプロジェクトです。
注3 苗プロジェクトへの協賛は、正福寺にお声掛けください。お寺で募った義援金と合わせて、苗プロジェクト主宰の蛯名隆三さんにお届けします。
|